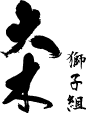獅子舞の担い手であっても
獅子頭がどのように作られているのか
天狗や烏天狗も、どのようにして出来上がっているのか
知らない人が大半だと思います
僕自身もそのうちの一人だったわけで、
個人的な写真活動などをしていなかったら
おそらく一生知らないまま終わってたのかも?
と思ったりもします。
ということで、せっかく職人さんから知ることができた
烏天狗の制作過程(一部)をご紹介いたします
まずは、、、

この塊は何だと思います?
そうこれが、獅子頭や面の形を成している紙、、、
和紙なんです
和紙といっても年代物の和紙。
古くは江戸から大正、昭和初期もあるのかな?
帳簿などに書き留める為、和紙で管理していた時代の年代物。
この時代の和紙は、とても丈夫なのだそうです。
それを濡らして一塊になっているのがこの写真
そして、、、

それを伸ばして~、伸ばして~
広げていきます。
この時点で破れることがないのが
年代物の和紙
そして伸ばした和紙を、、、

粘土で作られた烏天狗の型の上から被せて
押して押して形づくっていきます。
この作業もけっこう大変で、
ただ被せればいいというわけでもなく
細かな作業が途中ありました。
そして、、、

一塊の和紙が、このように最終的に烏天狗の面の形になりました
これはあくまで一部の作業工程なので
型から抜いた後、色々と作業はあります。
なかなか目にすることのない作業工程を見させてもらえて
獅子頭や面の大切さというか
職人さんの手によって生まれた物を
もっと大事にしていかないととつくづく思いました。
職人さんの話を聞いてるだけでも、制作へのこだわりが半端なく
そのように作られた道具を粗末に扱わないよう
気をつけていかないとと思います。
職人さん、これからも獅子頭、面のこと等々
学ばさせてもらいますね (笑)
(笑)