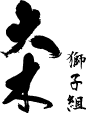ここ数年、新聞記事やイベント情報など、「香川県の獅子舞」という言葉をよく目にするようになっています。
ふと「香川県の獅子舞」とはなんだろ?
と、思ったので考えてみました。
このブログでは、大木獅子組のサイトではありますが、管理人が県内各地へと訪れた祭りや獅子舞を不定期ながら書かせてもらっています。
県内を西から東へ巡っていますが、どの地域もその土地柄の特色が出ていて、とてもいい刺激をもらっています。
![あやうたふるさとまつり[ 2017年11月5日(日)]](https://i0.wp.com/sanuki-shishimai.info/wp/wp-content/uploads/2017/11/IMG_1455.jpg?resize=450%2C300&ssl=1)
「香川県の獅子舞」と一括りにして、それらの地域の獅子舞を説明できるのかといわれると、、、
正直自信がないです(^^;)
では、香川県の獅子舞を全体的に見て、全て共通しているところはどこなのか、、、
![大木獅子組[獅子頭(修理後)]](https://i1.wp.com/sanuki-shishimai.info/wp/wp-content/uploads/2016/09/DSC_0671.jpg?resize=450%2C253&ssl=1)
「張り子の獅子頭」
だと思われます
※高松市香西町や、古くからの獅子頭が伝わっている地域などでは木彫りの獅子頭を使用されていますが、ここでは広く全体的に見てということで、申し訳ありませんが割愛させていただきます。
いやいや、鉦や油単があるだろ!
![獅子舞 [ 香川県仲多度郡まんのう町 ]](https://i2.wp.com/sanuki-shishimai.info/wp/wp-content/uploads/2016/12/img03.jpg?resize=450%2C300&ssl=1)
という声も上がるかもしれませんが、鉦がない地域も沢山ありますし、油単ではなく毛の獅子も土器川周辺地域では多く見かけます。
獅子舞の系統によって、使われる鳴り物の種類も変わってきますので、全て共通して同じ使われ方をしている鳴り物は、香川県の獅子舞では今のところ見たことはありません。
「讃岐獅子頭」
香川は全国でも獅子舞の盛んな地域です。
神社の祭礼に使われる獅子頭は、顎、耳、取っ手など一部を除き、張子の手法が使われています。
粘土の型に和紙を張り合わせ、型抜きをした後、胡粉や漆で素地を作り装飾を施します。
軽量で丈夫な乾漆作りが大きな特徴です。
香川県のサイトでは、香川県の伝統工芸として獅子頭をこのように紹介されています。
「香川県の獅子舞」を紹介するのであれば、、、
香川県の伝統工芸でもある、軽量で丈夫な乾漆作りの張り子の獅子頭を使い、その地域に伝わっている獅子舞を祭事で奉納をしている。
獅子舞の曲や、使われる鳴り物、獅子の油単(獅子の胴布)は地域によって様々で、舞も含め地域の特色が色濃く出ている。
でしょうか?
もっとうまくまとめれる文章力があったらよかったのですが(^^;)
ということで、このようにあれやこれやと考えても、、、
これぞ香川県の獅子舞!
といえるような代表的な獅子舞を、地域によって文化が違う香川県では見つかるわけもなく、言うなれば、張り子の獅子頭を使った様々な系統の違う獅子舞が伝わっているのが、香川県の獅子舞のいいところ、というとこでしょうか(^^)

最後に葛原でまとめさしてもらいますが、葛原4組ともまったく違うリズム、獅子舞を毎年奉納をしているというのもこの地域の特色です。
大木獅子組の獅子舞も、似たようなリズム、舞いをしている地域と出会ったことはありませんので、その組の獅子舞で完結しているというのも、先代達が築き上げた葛原の特長的な文化なのかもしれません。
この小さな地域でさえ、それぞれの獅子組で違っています。
日本一狭い県で、様々な獅子舞が生まれたというのもなんだか凄い話だと思います。
結局は、香川県の獅子舞文化は凄いなとなりますね(笑)